| |
 |
| �G�L���m�V�Q�n |
| �� |
 |
| �s�s���܂��Â���A�m�o�n���s�������A�Z���^���w�i�Z�́E�o��j�A�A�[�g�E�N���t�g�E�f�U�C���ȂǂɊւ��G�����f�ڂ��Ă��܂��B����̂Ȃ��̂����̂��́^���Ƃ����́A�������̎v�l�^���s���y�����N�����Ă���܂��B |
|
 |
���G�L���V�P�V�@25/12/22
�@�����i12��20���i�y�j�j�A�����E���c�i���FTIME SHARING
���c �����{�r���j�ő�{�����Y����̉̏W�w���̗����x�i�Z�ԏ��сA2025�N�j�̔�]��J�Â���܂����B�����i��͕x�c�r�q����i�܂Ђ��j�A�O���̃p�l���f�B�X�J�b�V�����̃p�l���X�g�́A�ɓ����݂�����i�܂Ђ��j�A�]�c�_�i����i�����j�A����x�q����i����j�Ɏ���4���A�㔼�͉�ꂩ��̔����𒆐S�Ɉӌ��������s���܂����B�Ⴂ���ォ��x�e�����܂ŁA60���قǂ̎Q��������܂����B�ȉ��ɁA���̔������������Ă��������Ǝv���܂��B |
 |
 �@���t���������߂���2��20���i�j�A���̉̏W�͂킪�Ƃɓ͂��܂����B�������J����ƘZ�ԏ��т炵���Z���X�̈���ŁA�����Ȃ��A�ƁB�����ł����Z���X�Ƃ́A�P�ɕ����I�ȃf�U�C���̂��Ƃł͂Ȃ��A�ҏW�ҁE�F�c�슰�V����́A����v���f���[�T�[�Ƃ��Ă̂���B�����āA���F���Z���A俐F�Ƃ������炢���̂ł��傤���A����ȐF�̑тɒu���ꂽ���c�C�O����̕��́B�u���Z�̂���̌���Z�̂ւƗ���鐅���̂ЂƂɁv�Ƃ��������o���́A������Ɠ���������ȁA�Ǝv�킹�܂����A�������ē���͂Ȃ��A�ƂĂ��_�炩��7�s�B�����A�������B�̏W���܂Ƃ߂�Ƃ������Ƃ́A�Z�̂͂ЂƂ�ł�����̂ł͂Ȃ��A�����̐l�Ɏx�����Ă���A���̂��Ƃ����炽�߂Ď������邱�ƁB�����Ő����Ȑl�́A������A������������莩�����k���A�����Ă������Ƃ��ł���B��{����͂����Ƃ���Ȑl���낤�ƁA�̏W��ǂ݂͂��߂�O����v�����̂ł��B�Ȃ܂��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�i�u���Ƃ����v��ǂނƁA�u�c�̏W�̏o�łɌ����ē����A�悤�₭�����̉̐l�Ɏx�����Ă��邱�ƂɋC�Â����c�v�Ƃ���A�����܂����B�j �@���t���������߂���2��20���i�j�A���̉̏W�͂킪�Ƃɓ͂��܂����B�������J����ƘZ�ԏ��т炵���Z���X�̈���ŁA�����Ȃ��A�ƁB�����ł����Z���X�Ƃ́A�P�ɕ����I�ȃf�U�C���̂��Ƃł͂Ȃ��A�ҏW�ҁE�F�c�슰�V����́A����v���f���[�T�[�Ƃ��Ă̂���B�����āA���F���Z���A俐F�Ƃ������炢���̂ł��傤���A����ȐF�̑тɒu���ꂽ���c�C�O����̕��́B�u���Z�̂���̌���Z�̂ւƗ���鐅���̂ЂƂɁv�Ƃ��������o���́A������Ɠ���������ȁA�Ǝv�킹�܂����A�������ē���͂Ȃ��A�ƂĂ��_�炩��7�s�B�����A�������B�̏W���܂Ƃ߂�Ƃ������Ƃ́A�Z�̂͂ЂƂ�ł�����̂ł͂Ȃ��A�����̐l�Ɏx�����Ă���A���̂��Ƃ����炽�߂Ď������邱�ƁB�����Ő����Ȑl�́A������A������������莩�����k���A�����Ă������Ƃ��ł���B��{����͂����Ƃ���Ȑl���낤�ƁA�̏W��ǂ݂͂��߂�O����v�����̂ł��B�Ȃ܂��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�i�u���Ƃ����v��ǂނƁA�u�c�̏W�̏o�łɌ����ē����A�悤�₭�����̉̐l�Ɏx�����Ă��邱�ƂɋC�Â����c�v�Ƃ���A�����܂����B�j
�@�����������l�͂킩��Ȃ��^�킩��ɂ����l�������āA���e�p��2�`3�����x�̏��]���������Ƃ�����킩��Ȃ��������Ă���������B�����ꌾ�A�����Ȃ��A�Ƃ��������Ȃ��悤�ȁc�c�B�w���̗����x������Ȉ���ŁA�ނ�_��ۑ������܂����A�������A���̏W�͂���h���ɂ��炯�o���Ă��܂����́B��������\��������Ă������Ƃ��A���҂Ɠǎ҂̊y����������ƂȂ̂��Ǝv���܂��B
�@����ł����̉̏W�ɂ���2�_���������A1�́A����ɂĂ��˂��Ɍ��������Ă���A������Ă��˂��ɋd������Ă���Ƃ������ƁA1�́A�]�����ɂ��Ă���Ƃ������ƁB�������ʂ̊p�x���炢���ƁA�ʒu�̂�����A�����̂�����Ƃ��������́^���Ƃ������ƒ���Ă����A�傫�ȉ����A�����Ƃ��������Ƃ������������ł͂Ȃ��A�ł��A��Ƃ����ƈ��Ղ�������Ȃ�����ǁA��ɂ������������ӂ��ƒ��Ă����B�������i���̐ڑ��������������ǂ����킩��܂��j�A�S�n�悢�ْ����������āA�ǂݏI������Ƃ��ɁA��͂�A�����A�����̏W���Ȃ��A�Ǝv���A����Ȉ�����Ǝv���܂��B
- �J�Ȃ�Ȃ������ł��˂ƌ��ꂵ�莆�@�n�����ʂ悤�ɂƂ��܂�
- ���������̂̑����Ă��̐^�����ފw�҂̂悤�ɗ�������
- �ݍs�̏��ɂ��ڂ��Ăށ@���B�X�R���e�B���D���Ȃ̂ł���
- �c���Ƃ����ɔG��Ă���H�n�̂������X�̖��O���ς��
- �܂��₩�Ɍ��͍������̊X�̂�������̍������
- �A��Ȃ��Ă����̂��Ɩ₦�����ƌ������ɂ���ЂƂ̖��̐���
- �h�C�c�ɂ͂�������܂����ƉR���������������{炉�悤��
- �z�܂ɋl�߂�Γ݊�ƂȂ�قǂ̖{�g���ċ����Ɖ��
- �Ď��߂����̊K�i�����Ŏ�����Ɛ��͗}���Č�����
- �����܂��ɉĂ��Ȃ��������Ƃɂ���J�~�炵�߂ċ㌎���
- �������_�����i����͎O�K�j�F�̒�����݊�����邪����
- �G�ꂽ��Ί��d�����Ă��܂����낤���~�͉Ԃ���Ȃɂ���
- ���������̏t���Ɏ����܂����ƒ������蓯���̒��C�̂���
- ���O�������܂܂ɉz���Ă��ė����X�����X�֓��肽��
- ���������Ȃ�Β��̟��ލ��I���F�̃C���N���l�߂�
- �����L���{�͖߂��ʈ������ǐ�ł����ǃt�[�R�[������
- ��̂���X�̕�炵�̂����邳�Â��_�C�j���O�e�[�u�����^��
- �t�x�݂Ȃ�L�����p�X�̐}���قŖ���ʐl�͊L�̂��Ƃ���
- ���Ԃ��͌��̗����l�Ɖ�\��f�薰�葱����
- �����Ⴍ����̃��V�[�g�Ђ낰�䂭���Ƃ��v���ʏ\�N�������ĂȂ�
�@20�������܂����B1��ڂ́A�����̍�i�B�u�J�Ȃ�Ȃ������ł��ˁv�B��̓I�ł����A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������ꂽ�莆�Ȃ̂��킩��Ȃ��̂ŁA���̃t���[�Y�̈Ӗ��͓ǎ҂ɂ͂킩��܂���B�������������҂ɂ��c�c�B�Ƃ܂ǂ��₽�߂炢�̂悤�Ȋ���̊j���̂��̂�������܂���B�Ă��˂����ƐT�d���ł��́^���Ƃ���钘�҂̖��͂��킩����Ǝv���܂��B
�@19��ڂ̓^�C�g���ɂȂ������B�u���̗����v�͑��݂��Ă��邯��nj����Ȃ��A�����Ȃ�����Ǒ��݂��Ă�����́B�u�l�Ɖ�\��f��v�B�l�ƂȂ����Ă��邯��ǐ��Ă���B�Љ�⑼�҂Ƃ̊u����Ƃ��������U����������܂��A���������`�ʂ̂����������͓I�ł��B���҂̃x�[�X�Ƃ��������܂��Ƃ������A����ɂ����ΐM�����������Ă�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@1��ڂ̂悤�ȍ�i�������ɒu���A19��ڂ̂悤�ȍ�i����^�C�g�������B��͂�A�����̏W���Ȃ��A�Ǝv���܂��B
|
| |
|
 |
���G�L���V�P�U�@25/11/19
 �@�uGALERIE
SOL�v�i�����s������j�ŊJ�Â���Ă��鎛�c�a�K����̌W�u���R�ώ@�̕��@�v�i����F2025�N11��17���`29���j�Ɏf���܂����B �@�uGALERIE
SOL�v�i�����s������j�ŊJ�Â���Ă��鎛�c�a�K����̌W�u���R�ώ@�̕��@�v�i����F2025�N11��17���`29���j�Ɏf���܂����B
�@���̂��Ƃ͈���I�ɑ����グ�Ă����̂ł����A��������͈̂ӊO�ƍŋ߂ŁA���N��6���B�����Ɛ���w���Z�ɂ̌��J�u���̎��Ƃ��I���A���傤�Ǔ������ԑтɎ��Ƃ��Ȃ����Ă����吼�~�V����i�����w�A�S�g���N�w�j����u�ꏏ�ɂ������т��v�Ƃ��U��������������o�Ă��炭�����Ă���ƁA�ߌ�̎��Ƃ̂��߂ɗ���ꂽ���ɂ����肨������̂ł����B���h�����傤��������ƁA������͎��̕����̑c�ꂪ�ӔN���߂������y�n�B�Ȃ��ƂĂ����ꂵ���C�����ɂȂ�܂����i���{�l�ɂ͐\���グ�܂���ł������j�B���̂Ƃ����傤�ǁA�u���؉@
�M�������[�v�i�����s�`��j�ŌW�uObservation of NATURE�v�i����F2025�N5��31���`6��28���j���J�Â���Ă��āA����A�����^�̂ł����B�傫�ȍ�i�������A���|����܂����B�����ȍ�i������A�茳�ɒu���Ă��������ȁA�Ǝv�������̂��������̂ł����A���̃G�l���M�[���~�߂邱�Ƃ��ł����A���̂Ƃ��͂�����߂��̂ł��B
�@����͂ǂ�ȍ�i�Əo��邾�낤�ƁA�M�������[�Ɏf���܂����B�ǂ������V����^�����ȋ�Ԃ͂ƂĂ��������A��i����������ƁA�����Ă��炩�ɂ���܂����B���l�ŁA�ǂ�����͓I�ŁA�茳�ɒu���Ă��������ȁA�Ǝv����i������������������āA�����Ԃ�Y�݁A�Ō�͍�҂ɂ����k���A1�_��I�т܂����B
�@�u�t�ł�悤�ɁA�x��悤�ɕ`���ꂽ�G�悽���B�v�B����̌W�̃��[�t���b�g�ɂ���t���[�Y�ł��B�ƂĂ��V���v���Ȃ���ł����A�u�t�ł�悤�Ɂv�u�x��悤�Ɂv�Ƃ����l�Ԃ̌������Ƃ�����Ƃ̉������y�����A����Ȍo�������邱�Ƃ��ł����A�M�d�ȂЂƂƂ��ł����B
|
| |
 |
�ǂ������V����^�����ȋ�Ԃ��������uGALERIE
SOL�v�B |
|
| |
|
 |
���G�L���V�P�T�@25/10/22
 �@�����p�F����ɂ͂��߂Ă�������̂́A1991�N�ɏ㈲�����ى̏W�w��Ԙa���x�i���q�����[�j�̏o�ŋL�O��ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B����30�N�ȏ���O�̂��ƁB���������30��㔼�A���͂��傤��30�B���̌�A����ł��ꏏ������A�Z�̊W�̍Â����ł�������肵�āA���낢��Ȃ��b�����Ă��������܂����i��������̂��b�͂����h���I�ł��j�B�ŋ߂́A�����Q�����Ă��鉡�l�̐l��̌�����ɂ悭�����^��ł��������܂��B����ȉ�������̉̏W�w�v���V�s�X�x�i�Ȃ���ݏ��[�A2020�N�j�́A��������炵�����̂ƃe�[�}�̈���ł��B �@�����p�F����ɂ͂��߂Ă�������̂́A1991�N�ɏ㈲�����ى̏W�w��Ԙa���x�i���q�����[�j�̏o�ŋL�O��ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B����30�N�ȏ���O�̂��ƁB���������30��㔼�A���͂��傤��30�B���̌�A����ł��ꏏ������A�Z�̊W�̍Â����ł�������肵�āA���낢��Ȃ��b�����Ă��������܂����i��������̂��b�͂����h���I�ł��j�B�ŋ߂́A�����Q�����Ă��鉡�l�̐l��̌�����ɂ悭�����^��ł��������܂��B����ȉ�������̉̏W�w�v���V�s�X�x�i�Ȃ���ݏ��[�A2020�N�j�́A��������炵�����̂ƃe�[�}�̈���ł��B
- �����ꂵ�܂Ȃ��Ă�������ނ����N�߂��͂�}�₫�̂��͑��ӂɂ�����@�@�����p�F
- �@�a���ɂ��Ȃ��̔����͂������������B
�����l���������Ǝv���Ƃ��������Ă킽���̎�������Ă���Ȃ�Ƃ���
- ���肩�������Ȃ��̗͂͂��̂����ア�悷���������₽����
- �@�����A�����Ŏ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ȑ��ʼn�����ɍ������B
�C�i���イ�j��������Ȃ��邽�߂ɂ���ȏ�ꂵ�܂��Ȃ����߂ɁA���Ȃ���
- ����悤�ɕ��ɂ݂ǂ肪�h��͂��߃A�g���G�ɂ������t�����Ă���
�@�܂��A��A�u���z�Ԋق܂ń������E�����C���v����5������܂����B�����C������̐��O�Ō�̂��{�ł���̏W�w�g�D�I�l���x�i�Ȃ���ݏ��[�A2017�N�j�́A�������ďC���땶�̎��M�Ȃǂ��Ȃ��������́B�w�g�D�I�l���x�̊��s��6���A�S���Ȃ�ꂽ�̂͂��̔N��11���ł����B1��ڂ́A�Ⴂ�����炸���Ǝ��i���Ă����i�u���Ƃ����v�j���炱���́A��������̕��̂������Ȃ����1��Ǝv���܂��B4��ڂ̎����́u������v�́A�����܂ł��Ȃ��A�v�l�E���g�Ԃ���ł��B
- �������x�m���݂ė��܂����Ɨ[���̑����������Ă��ǂ�ʕꂪ
- ��ɂ͎O�l���q�������Ƃ��������Ɨ����ɕ�͔K�����݂���
- �@�ӂ�������܂ɕꂪ�����B
���ɂ͉���̂��Ɩ��ꕃ�͂������̉_�̂킭���Ȃ��Ƃ�����
- �w�������������ӂ邦�Č��Ղ���̂ނ����̋ȂȂ��ꂾ��
- �킩��₷�����l���蘻����Ē��̊Ԃ̕�ɂ��ǂ镽��
�@����̕����r�܂ꂽ��i�B���낢��Ȋ���s�������Ă���͂��ł����A���ɂ����鋗�����̂���悤���m���ŁA�ǎ҂ɐe�����͂��܂��B
- ���̊������ǂ���݂͗z�̂ɂ����������������悤�ɃX�[�v��
- �܂��͖��邱�ƐH�ׂ邱�Ɩl�������ڂ������ł��邽�߂̖�
- ���ꂼ��ɂƂ���ǂ��ׂ��Ό������ĂΑ傫�Ȃ�����w����
- �������y���Ȃ邽�߂��݂͂����������⛌�ЂƂ�����������
- �[������ɕ�܂ꂫ�݂̓L�b�`���ɂ����t�̃L���x�c�ςĂ���
�@�����āA������l���r�܂ꂽ��i�B3��ڂɂ���悤�ɁA�����炱���V�N�ŁA�����炱�����₩�Ȃ̂��Ǝv���܂��B
- ���m��ʒj�̏��i�āj�Ɋ������Ȃɂ��܂����ɉ��������炤�Ƃ�
- ���̉_�̂������܂�Ŋݕӂ܂ł����ƈ������Ȃ����@��
- �J�ɂ�����n�Ɍ��悹�Ă����y�Ɋ҂肽���̂ƕa�t������
- �L�b�`���Ƀp���Ă��Ă���N���ė����o�����̉J�̂��Ƃ���
- �ʊw�H�ɂ͂��Ⴎ���X�V���b�^�[��������ԉ��̒��̂��͂悤
�@�Z�p�I�ȓ��F���ЂƂ���������A�Ђ炪�Ȃ̎g�����̂��܂��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̊��������������炵�āA���炩�ȕ\�L�œǎ҂ɓ͂���B
�@�u���Ƃ����v�ɁA�u�u�v���V�s�X�iprecipice�j�v�Ƃ́A��@�I�ȏ�f�R�̈����ŁA���̐��N�A�W�c�I���q���≫��̊�n���A�����̍ĉғ��⌛�@�����ȂǁA�����͋}���Ɋ낤�������ւƑǂ��͂��߂��悤�Ɏv���B����ȈßT�Ȏ���ւ̚g�����߂ďW���Ƃ����v�Ƃ���܂��B��������炵���Ǝv���Ȃ���A�u�ßT�Ȏ���v�ł����Ă��A���́^���Ƃ𐴁X�����d������Ă����A�������������炵���Ȃ̂��Ǝv���̂ł��B
|
| |
|
 |
���G�L���V�P�S�@25/8/26
�@���g�Ԃ���̉̏W�w����ł��x�i�Ȃ���ݏ��[�A2020�N�j�ɂ��Ắ��G�L���U�Q�V���ʼn����Љ�܂������A������s���ꂽ�̏W�w�ΐF�̐l�x�i���Ёj��q�ǂ��A���炽�߂ēǂݕԂ��܂����B
- �A�C�X�e�B�[�̖������Ɏc���Ėҏ��̊X���}���@�w�ւƁ@�@��
�g��
- ��܂�����瀂���瀂���Ė��z�i�܂Ӂj�̂��Ɠ\����Ă���ܑ��H�̏�
- ��X���܂Ō��Ђ����Ƃ������ďI��Ă݂�܂ڂ낵�̂₤
- �t�F�C�X�^�I����ɂ��Ă��t�̖�́@������Ă��₤�ŋ��������₤��
- ���ɂނ��Ђ��̏������͔����̐������́@�������̌��̊Ⴉ���
- �v����K�ɂ��킽�������ĂԐ��������̂��ƕ������Ƃ̂���
- �ʂ�߂������̋L���́@���ǂɉf�邠�܂��̂Ђ܂͂�̉e
- �킽�����{���̂킽���ɏo��ӂƂ�������̂��ƍ����v�ӂ��Ƃ���
- ���x�قȂ��l���ڗ����f�����n��Q�O���K��茩���
- �a�ނ��݂̏А����Ƃ��ɂ킽���͂ǂ����Ă������x��ď�
�@���Ƃ����ɂ́A�u��Z��ܔN�~�A��N�̌��N�f�f�̌��ʁA�v�͂����Ȃ薖������鍐����܂����B�i���j�ꎵ�N��ꌎ��\�O���A�v�͐��ɋA��ʐl�ƂȂ�܂����v�Ƃ���܂��B�����2���\���ŁA�܂��u�T�v����10������܂����B
- ���̐��ɂ��Ȃ������Ȃ��Ƃ��ӂ��Ƃ̂��疀�d�s�v�c���܂͂��ɂ���
- �Ԏ�ƂȂ�Ė邲�Ƃɐ�����镔���ɂ��ӂ�Ăނ����ւ鋟��
- �e���r�����ꌎ�i�ЂƂ��j�͉߂����E��m��˂ǐ���ԂƉ�b��
- ����ł��邠�Ȃ��͕��Ԃɂ킽�����͐����ĉ�������Е�����
- ����̎��͂��߂��ߋ������v�̎��͒P���Ȃ炸���䂭���䂭�Ƌ���
- �u�C����A���͂₤�A���͂₤�v�ƒ����ƂɌ��ӈ�e�Ɍ������_���̂₤��
- �R���b�P����@���̂Ȃ�ł��Ȃ����Ƃ́@�Ȃ�ł��Ȃ����̃R���b�P���
- ����̂����ւ͂ɂ��ޏ��N�̌㔼������ꌩ�͂���
- �Ԃ̉����S�ɂނ��т�H�ӂ��͏t�̂܂Ђ���lj��̂��Ƃ�
- �킽�����̖j���ۂۂG�点��͌ς̉J�̂̂���̂��Â�
�@�����āu�U�v����A���G�L���U�Q�V���ł��Љ��4��ȊO�̍�i10��������܂����B
�@���݂Ƃ������炷������U���Ɏv���邩������܂��A����́A���Ƃ��u��܂������`�v�u���ɂނ��Ё`�v�u�ʂ�߂����`�v�Ƃ�������i�ɂ悭�\�ꂽ�A����̌������������Â��Ɏx�����Ă���̂��Ǝv���܂��B�����炱���A�u����ł���`�v�u�u�C����A���͂₤�A���͂₤�v�`�v�u�Ԃ̉��`�v�Ƃ�������i���A�Â��ɓǎ҂ɓ͂��̂��Ǝv���܂��B
|
| |
|
 |
���G�L���V�P�R�@25/8/18
- �ԕ��Ȃق��ڂ��e���ɂ���@�@�a���c�q
- �_�a�̊^�������ďt��
- �n������F�̒_���
- �R���Ɋ��u���Ă���H��
- ���̒܂̉����ւ����̓���
- �����⋍�����ɖ������̑�
- ⡂̂��Ƃ�Ə�肵�L�̏�
- ��͂����킳������
- �ǂ��ɂł��s���邳�т��������P
- ��������Č����ɂ��₩����
- ���Ȃ̐l�ɉJ�̍��\��
- ���������ɍ��肵�
- ���̖��Y�ꂵ���Ɠ����ڂ�
- �������̂킪�藣�������̐�
- �藣���ƌ��߂��鐗�����肯��
- �����܂ŕ������͂��̏t�x��
- �E�Ђ���͂����Ï��̂ɂقЂ���
- ��Ɍ�������������
- ���Ԃ��C�l�ɏ������ڂƌ���
- �ڂނ�č������Ȃɂ��~��
 �@�a���c�q����̋�W�w����x�i�ӂ���A2024�N�j��������܂����B�w�N�ȁx�i�ӂ���A2015�N�j�ɑ����A9�N�Ԃ�̋�W�ł��B�w�N�ȁx�ɂ��āA�u��͂肤�܂���Ƃ��Ȃ��A�Ƃ��炽�߂Ďv�����̂ł����v�Ə����܂����i�G�L���T�V�P�j���A�w����x�������v���Ŕq�ǂ��܂����B �@�a���c�q����̋�W�w����x�i�ӂ���A2024�N�j��������܂����B�w�N�ȁx�i�ӂ���A2015�N�j�ɑ����A9�N�Ԃ�̋�W�ł��B�w�N�ȁx�ɂ��āA�u��͂肤�܂���Ƃ��Ȃ��A�Ƃ��炽�߂Ďv�����̂ł����v�Ə����܂����i�G�L���T�V�P�j���A�w����x�������v���Ŕq�ǂ��܂����B
�u���̖��Y�ꂵ���Ɠ����ڂ��v�u�������̂킪�藣�������̐�v�u�����܂ŕ������͂��̏t�x���v�B���Ƃ����ɂ́A�u��Z��Z�N�O���A�\�N�ɂ킽�镃�̎����삪�I�������}����ɂ����苳�E���������B�i���j���ĂȂ��قǂ̎��Ԃ�����ʼn߂������ŁA����̗��e�Ƃ̎��Ԃ͂��������̂Ȃ����̂ɂȂ����v�Ƃ���܂��B
�@�u�n������F�̒_��Ёv�u���̒܂̉����ւ����̓����v�u���Ԃ��C�l�ɏ������ڂƌ��Ɓv�B���Ƃ������́^���ƁB�u�ǂ��ɂł��s���邳�т��������P�v�u���������ɍ��肵��v�u�ڂނ�č������Ȃɂ��~���v�B�l�Ƃ������́^���ƁB����́A���l�ȖL���������������Ă�����i�����ł��B
|
| |
|
| |
|
 |
| ���G�L���V�P�Q�@25/7/8
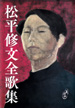 �@�w�����C���S�̏W�x�i���Ёj�����s����܂����B�S���Ȃ���7�N���B�Â��̏W�͂Ȃ��Ȃ���ɓ��炸�A�����̕����҂��]��ł�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�w�����x�i�发�فA1979�N�j�A�w���n�̋����x�i�发�فA1983�N�j�A�w�����x�i�发�فA1995�N�j�A�w�H�i�̂�j�x
�i���q�����[�A2007�N�j�A�w�g�D�I�l���x�i�Ȃ���ݏ��[�A2017�N�j��5���̉̏W�ɉ����A�����̕сA��W�w���̊G�x�i���ƔŁA2010�N�j�A���W�wRera�x�i���ƔŁA2012�N�j�����߂��A���N���i�쐬�F�������Áj���Y�����Ă��܂��B �@�w�����C���S�̏W�x�i���Ёj�����s����܂����B�S���Ȃ���7�N���B�Â��̏W�͂Ȃ��Ȃ���ɓ��炸�A�����̕����҂��]��ł�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�w�����x�i�发�فA1979�N�j�A�w���n�̋����x�i�发�فA1983�N�j�A�w�����x�i�发�فA1995�N�j�A�w�H�i�̂�j�x
�i���q�����[�A2007�N�j�A�w�g�D�I�l���x�i�Ȃ���ݏ��[�A2017�N�j��5���̉̏W�ɉ����A�����̕сA��W�w���̊G�x�i���ƔŁA2010�N�j�A���W�wRera�x�i���ƔŁA2012�N�j�����߂��A���N���i�쐬�F�������Áj���Y�����Ă��܂��B
- ��̂₤�ɖ���Ή肮�ގ}�X�̓��ǂ𐅂̂ڂ�Â����@�@�����C��
�@����́A�܂�w�����x�̊����̍�i�ł��B���炩��6���̏���ł͂��܂���������B�����͉̂��^�N���B
�@�����āA���g�Ԃ���̉̏W�w�ΐF�̐l�x�i���Ёj�����s����܂����B �J�o�[�̕\4�ɂ͕��������B�e���ꂽ��������̎ʐ^���A���Ԃ��ɂ͏�������̊G���i�u����ꂢ�����v���u����Ă��܂��B
- �ǂ�̎��̗��X����̖ؖ��ɖڗ��G�i�Ƃ��j�ƂȂ肽��@�@��
�g��
�@�����̍�i�ł��B��������́u��̂₤�Ɂ`�v�Ƌ���������ۂ�����܂��B�u��̖ؖ��v���A�s���A�u�₩�ł��B
�@��N12��16���A�u�Z�̍�i�ߍ�20�v�̃y�[�W�Ɂu�����C�����S���Ȃ��Ď��Ԃ��o�����Â��Ȃ������i�u������v�ɖT�_�j�v��u�����̂ŁA�ӂƎv���āA�Z�����͂������܂����B���̃y�[�W�͍X�V����ƍ폜���Ă��܂��̂ŁA�ȉ��ɓ]�ڂ��Ă��������Ǝv���܂��B
��
�@�����C�����S���Ȃ����̂�2017�N11��23���B�������̂�7�N�̎��Ԃ��o���܂����B��������W�w���̊G�x�i2010�N�j�𑗂��Ă����������Ƃ��͋����܂����B��������́u�G���������p��]�ƌ��̉r�݁v�i�����u��z�|��L�ɑウ�āv�j�Ȃ̂ł�����B����ɋ������̂́A���߂�ꂽ��i��1958�N�i12�j����1965�N�i19�j�܂ł̂��̂ł��邱�ƁB�u�ɒ��ރg���b�N�ďI��v�u�����݂̉��ɋ����色�O��v�u�n����Ԃ��ܓ����o���������v�u���̊G�͎d�オ�炸�ċx�ݏI�͂�v�u�т̂��Ƃ��W���t�̌Q������Ă䂫�v�B����������i��10��̏��N�������Ă����Ƃ������Ƃ͂������������ł������A�u�Ή�i��������j��H�Ӕn��A���s�ցv�u���Ԃ��Ԉ���ʼnďI�͂�v�u�D������ŗ[�����Ђς����v�Ƃ�������i�̐V�N���Ɋ������܂����B
�@�u����̎}�𗣂ꂵ�ЂƂЂ�̉e�Ƃ����Ȃ�t�̗��t�́v�u��ς݂đ��肽����Ƃ��Ƃ͂ɉԍ炭���Ƃ̂Ȃ����Ȃ�v�u���y�̂₤�ɑ��ɗ������Ă����Ӎs����̂��Ɓv�B�t�N���ɍ\�����ꂽ�ŏ��̉̏W�w�����x�i�发�فA1979�N�j�̍Ō�ɒu���ꂽ��A�u���肻�߁i���Z��`��㎵��j�v�̍�i�B��W�w���̊G�x����̐ڑ��̔��������v���܂��B�i2024.12.16�j |
| |
|
 |
���G�L���V�P�P�@25/6/24
- �Ă̂Ђ�ɕX���������点��Ԃ��Ԃ��Ǝ���ꂽ�q�́@�@�y����Y
- 瀎������e���ɂӂ�邵�����ɂĖl�̎肪�J�邭���������T
- �h��h��ƂȂ��������ď����Ă��邻�̎莆�̂܂��������邢����
- �킪��������u���Ă������ꂪ���܂ł����Ă�����Ȃ��܂�
- ����͖��̂��Ƃ����a���犱���ꂽ�܂܂̂��ڂ�͂��߂�
- �Ԃ���ł����ƍ���������ʼnč��h�̂�������������
- �a��݂ȗ��V�ɃC���^�[�t�H���������u���J�h�肵�Ă��悢����
- �킪�Ăɂ͂��������͂��肩��������r�Ȃ������ɂ܂�����
- �������̂̂��Ƃ��w�ԂƂ����Ƃ��̂������̂ɂ킪�Ƒ�����ꂸ
- �킽���ɂ͌����Ȃ��Ƃ����肢�����ӂɓ�C���Ȃւт̂���
- ���đւ��邽�тɏ������Ȃ�Ƃ̂����ɖ��镃�e
- �₪�ė���q���̂��߂ɒ��l�������ς��ɂ���قǂ̂�����
- ���������a�˂̂Ȃ�����Ƃ��Ďg��ꂽ�Ђƕ����͂���
- �Ђ���т邱�Ƃ͕|���Ƌ�����ΐ����D�����Ƃ��肩��������
- �y�b�g�{�g���̂Ȃ������ɂ�������Œ�ЂƂ��߂������
- �����ɖ����̂������ޗ��Ă��Ă����܂𑖂��Ă������ƂȂ���
- �ق�Ƃ��̂�������ɂȂ邨������̐l�`�Ă̂����̂ЂƂ�
- �����ɏZ�ޒN�������Ȃ����炢�����������܂��傤�A�A�p�[�g
- �܂�Ńp���݂����ł��Ȃ����킢�������Ă��Ȃ�������Ȃɖc���ł���
- �A���o�C����邽�߂����ɐ����邱�ƋC�Â��ΐX�̒��ɐ��ސl
 �@�y����Y����̉̏W�w�`��S�j�x�i�Z�̌����ЁA2023�N�j����20��قLj����܂����B �@�y����Y����̉̏W�w�`��S�j�x�i�Z�̌����ЁA2023�N�j����20��قLj����܂����B
�@�������������Ă���Љ�A���邢�͐������Ă��钬��Ƃ͂������ĒP���ł͂Ȃ��āA���������݂��ɋ��L���Ă���Ƃ������Ƃ�O��ɂ��Ȃ��Ɛ��藧���Ȃ����Ƃ������A���L���Ă��邱�ƂƂ��Đ����Ă���A���邢�͐������Ă���̂��Ǝv���܂��B�ł��{���́A���L���Ă���Ƃ͌���Ȃ��̂ŁA�܂肱�̈���́A����������Ă���l�Ԃ��A����p�x�������A����Ȋ����ł���Ƃ����A���҂̒Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����炱���A�����A�{���̗l�Ԃ��`����Ă���̂ŁA�ƂĂ����A���Ȃ̂��Ǝv���܂��B�����āA�S�n�����̂��Ǝv���܂��B
|
| |
|
 |
�G�L���m�V�Q�n |
|
 |